地域発、生活者と企業でアップデートするコミュニティ〜【メディアイノベーションフォーラム2019】パネルディスカッション
編集部
2019年11月19日、東京・有楽町のヒューリックホール東京にて、博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所による『メディアイノベーションフォーラム2019 DIRECT_ 多接点時代のつながり方』が開催。同研究所の研究員による最新の調査結果の発表やゲストスピーカーとのパネルディスカッションをもとに、次なるメディア環境の姿が解説された。
今回は、パネルディスカッション「地域発、生活者と企業でアップデートするコミュニティ」をレポート。キーノートでも挙げられた「自分ひとりではなかなかできないことができる」「訪れるだけ、買うだけ、何かをするだけで参加可能な仕組み」「企業が生活者とともに(ミッションを)実行する」という3つの観点をベースに、企業がコミュニティを通じて人々の生活や社会を直接変革している事例を紹介する。
【関連記事】「いい会話」が「いいブランド」をつくる〜【メディアイノベーションフォーラム2019】パネルディスカッション
【関連記事】多接点時代のコンテンツの作り方〜【メディアイノベーションフォーラム2019】パネルディスカッション

パネリストとして西日本新聞社 経営企画局 新メディア戦略室 兼 西日本新聞メディアラボ クロスメディア報道部の井関隆行氏と、博報堂クリエイティブセンター クリエイティブ・ディレクター 兼 東北博報堂 エグゼクティブクリエイティブ・ディレクター 兼 Local.Biz 代表の鷹觜愛郎氏が登壇。モデレーターを博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 上席研究員の新美妙子氏が務めた。
■甘さ以外の“価値”をつくるオフィス向けみかん配送「働くひとの西宇和みかん」
最初に鷹觜氏が、愛媛県・西宇和地域産みかんのオフィス向け配送サービス「働くひとの西宇和みかん」を紹介。

鷹觜氏:日本におけるみかんのトップ産地である愛媛県西宇和産みかんのブランディングの一環として、栄養士監修のもと、会議用・休憩用・デスク用といったオフィスのシーン別に選別し配送する「働くひとの西宇和みかん」というD2C型の地域農産品を企画した。

企画の背景について、鷹觜氏は次のように語る。
鷹觜氏:現在、農作物の流通は地元農協から全農(全国農協連合会)を経由して東京の大田市場に全量出荷され、仲買人から小売を経由してお客様の手にわたる。しかし現状は(作物が手元に届くまで)時間がかかるし、旬のまま食べてもらうには時間と移動距離がかかってしまう。できれば、作物を産地から直接食べてくれる方に届けられたらそれにこしたことはない。60兆円と言われる規模の食品市場のなかで、ネット流通が占める割合はわずか2%ほど。地域の1次産品(の直販)には大きな可能性があると思った。

鷹觜氏が着目したのは、作物の流通単位。みかん農家の人々から受けた言葉から、具体的なアイデアを思いついたという。
鷹觜氏:農家の方いわく、「昔は5kg、10kg入りのダンボールでみかんを買ってくれたが、いまは1kgに小分けされたみかんでも、なかなか食べてもらえない」。いまは単身世帯が多く、ひとりで10〜20個を購入するのは多く感じてしまうのではないか。そこで、現代の家族とも言えるオフィスの部署やチームへ、みかんを届けられないかと考えた。

届ける場所をこれまでの一般家庭や個人から「オフィス」へと転換させることで、届けるみかんの選別方法もあらたに考え直したという。
鷹觜氏:(一般的に)市場に出荷するさいは、サイズが大きく甘いものが一番価値が高く、糖度が減るにつれて商品価値が下がる。しかしデスクワークのときに求められる要素は、「甘さ」よりも「水分補給」が大事だったりする。甘さや大きさなど条件に応じて商品分類をしなおし、「会議のときに最適なみかん」や「デスクワークのときに最適なみかん」「休憩のときに良いみかん」など、栄養士の方と一緒に働き方にあわせて選別したみかんを届けることで、これまでにない新しい価値を作り出した。

「多接点になるということは『化粧まわし』を変えること」と鷹觜氏。
鷹觜氏:みかんに限らず、いまほとんどの産品は市場に出荷するときは大きさや「あるひとつの基準」で計られているが、届けられる場所に応じてその基準は変わる。生産地と生活者の関係が多接点になっていくことで、これから商品の価値は劇的に変えていくことができるのではないかと思う。
「オフィスにみかんを送る」という新たな接点を設けることで、商品を軸とした新たなコミュニケーションの創出にもつながると鷹觜氏は語る。
鷹觜氏:スーパーの陳列棚では値段情報が精一杯の「じぶん語り」になってしまう。オフィスにみかんを送ることで、産地のストーリーをしっかりと伝えることが可能になり、さらには、職場の人々にいろんなコミュニケーションを取りながら食べてもらうことで、ソーシャルメディアを通じて発信してもらえる。マス(コミュニケーション)とは違うかたちで、新しい「ファンづくり」が可能になる。

「働くひとの西宇和みかん」は、数量限定で販売した令和元年の初荷分がネット上ですでに完売。次期出荷分の予約も「かなりの数をもらっている」(鷹觜氏)という。
■LINEで新聞社と直接つながることができる 西日本新聞「あなたの特命取材班」
続いて井関氏が、SNSを通じてメディアと生活者が直接つながる場を設ける試み「あなたの特命取材班」を紹介。


井関氏:「あなたの特命取材班」は、生活者の悩みや疑問を新聞社の取材力によって地域の課題にし、報道していくという取り組み。LINEの公式アカウント「LINE@(現・LINE公式アカウント)」を活用して読者へ「調べてほしいこと、困っていることはありませんか?」と呼びかけ、メッセージ機能を通して寄せられた「調査依頼」を受けてプロの記者が取材する。
同 アカウントは約13,000人の登録者を抱え、これまで寄せられた依頼は約8,000件。その内容は暮らしの疑問や地域の困りごとをはじめ、組織による不正を内部告発するものもあるという。取材結果はWEBサイトをはじめ、Yahoo!ニュースなどの外部ポータルサイトへも配信されている。
「昔はハガキや電話で新聞社へ情報が寄せられていたが、いまはLINEで寄せられる時代。記者が持つスマートフォンへダイレクトに情報が寄せられる」と井関氏。
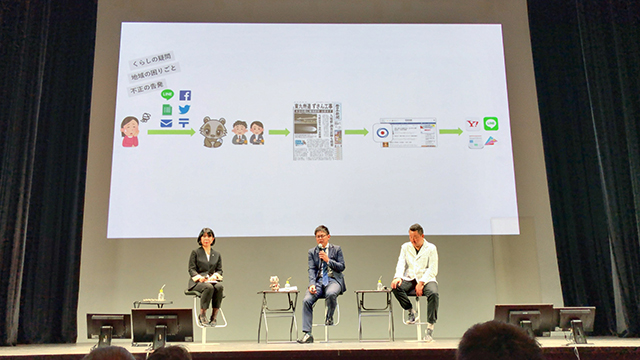
井関氏:(読者の)LINEのトーク画面には家族や友人にまじって西日本新聞がリストアップされている。「スマホを開いたら西日本新聞がいる」という距離感で、話しかけたら直接記者に通じるという距離感を作れているという点が新しい。
この「あなたの特命取材班」の取り組みによって、地元に関するさまざまなスクープ記事が生まれたという。具体的な事例を井関氏が紹介した。
井関氏:「近所の道路に朝早くから大型のダンプカーが止まっていて、(通行が)危険だ。調べてほしい」というLINEメッセージが届いて、記者が(情報提供者と)直接やり取りするなかで、現場の写真や情報が上がってきた。
「市民から見て危険である」という情報提供からはじまった取材であったが、調査を進めるうち、この問題の「もうひとつの視点」も浮かび上がってきたという。
井関氏:このケースでは、(路肩に停車する)ダンプカーの運転手側にも事情があることがわかった。福岡では(市街の)開発(工事)が進んでいるが、工事現場に入場まで待つ場所がなく、泣く泣くここ(近くの道路上)で待機せざるを得ないという事実が浮き彫りになった。結果、(地元住民と運転手)それぞれの立場で悩みがあるということを伝える記事になった。
社会的な問題にはさまざまな当事者が存在する。そのぶん多面的な視点を提示することで問題が解決に向かったり、メディアに対する新たな信頼が芽生えたりすることもあるという。井関氏は続ける。
井関氏:真夏に中学生からメッセージが送られてきた。「猛暑のなか体育祭の練習をしているが、学校で日焼け止めを塗ったら先生に怒られた。先生は帽子もかぶっているし、長袖も着て完全防備しているのに、なぜいけないのか(納得できない)」という内容だった。調べると、校則で「日焼け止めは(学校ではなく、あらかじめ)家で塗ってくること」と決めている学校が多いことがわかった。これをふまえて医師に取材し、「(いまの時期は日焼け止めが)とても必要なのでぜひ(随時)塗ってほしい」というコメントを得て、記事に掲載した。すると投稿者の中学生から「新聞掲載を楽しみにしています」とメッセージが届いた。(若者の新聞離れが取り沙汰される)この時代に中学生が新聞を楽しみにしてくれるなんて、とても嬉しかったのを覚えている。
「あなたの特命取材班」を通じて得た“気づき”について、井関氏は次のように語った。
井関氏:「SNSで言いたいことを発信できる世の中になっている」というが、誰にも言えない悩みのなんと多いことかと(「あなたの特命取材班」を通じて)気づかされた。これまで新聞社がやってきた「知るべき、知らせるべき」の報道に加えて、読者の「知りたい」ということに答えていくこの姿勢が大事だと感じた。
■「あな特」から全国の新聞社へ広がる「オンデマンド調査報道」の流れ
生活者がメディアに暮らしの疑問や地域の困りごとを相談するコミュニティを作り、それによって生活者が「知りたい」にこたえる「あなたの特命取材班」。そこには、多接点時代ならではのメディアと生活者の新たな関係性が見えてくる。生活者から新聞社にではなく、新聞社があな特通信員に直接アプローチして取材に協力してもらう動きが生まれている。

井関氏:(LINEの)プッシュ通知機能を通じて読者に取材協力を呼びかけたところ、情報を寄せられたケースも出始めている。以前「平成生まれで『キラキラネーム』(当て字や難読漢字などを用いて派手な読み方をする名前)を命名され、その後改名した経験のある人」を募集したところ、5分くらいで次々と情報が寄せられた。これまで天神(福岡の中心地)の地下街で探していたら絶対に見つからなかったような方々から、直接情報提供いただけた。
これまで「ネタは記者が足で稼ぐもの」とされてきたし、これからも変わらず重要な専門技術だが、読者とダイレクトにつながって、ともに報道を作っていくという新しい手法・コミュニティが生まれている。
こうした流れをくみ、「(読者が)知るべきこと」「(メディアが)知らせるべきこと」「(読者が)知りたいこと」をそれぞれやりとりし、取材活動を行う「ジャーナリズム・オンデマンド」というムーブメントが全国に広がっているという。

※2019年11/19時点
井関氏:西日本新聞単体の取り組みだった「あなたの特命取材班」だが、本紙の想定エリア外である広島などの地域からも取材依頼や情報提供が寄せられるようになった。「エリア外だからといって取材しないわけにはいかない」と中國新聞に連携を呼びかけたことをきっかけに輪がひろがり、現在は琉球新聞や東京新聞、京都新聞など全国各地の新聞社と調査報道のノウハウ共有や記事の交換を行う「JOD(Journalism On Demand:ジャーナリズムオンデマンド調査報道)パートナー」という取り組みに発展した。

■「少量多品種」×「多接点」でニーズと価値を上げる
続いて鷹觜氏が「日本版D2C(Direct to Consumer:製造元直販)」という観点から「働くひとの西宇和みかん」が社会に与える影響について語った。

鷹觜氏:これまでは「曲がったキュウリ」が市場に出回っていなかったように、大量に集めて大量に納品する形では規格に沿わないものは弾かれ、均一な形のものに揃えられてきた。しかし、実際には農作物というものはバラバラな形をしていて、ひとつひとつが個性を持って育っている。デジタルの機能を使えば、その個性をきちんと分けた形で「少量多品種」の作物を出荷でき、それを必要とする人たちに多接点で届けることができる。
「詰め方や仕分け方、届け方を変えることで多くの商品が増え、それぞれ求める人が増えることで商品価値が上がっていく」と鷹觜氏。日本の農業が抱える問題を、生活者が一緒になって解決していくことにもつながると希望をのぞかせる。
鷹觜氏:(農業におけるD2Cは)育ての親を日本中に作ることになると思っている。農業の分野は生産者の高齢化が加速しており、「いいものがあっても育てきれない」状況が続いている。ただ買って食べるのではなく、作物を軸としたコミュニティへと参加してもらい、現場の課題を一緒に解決することで(農家と生活者が一体となった)「ファミリー」として産地を支えていく形が作れるのではないか。
■生活に作用するコミュニティ 企業の可能性
今回のパネルディスカッションを、新美氏は次のようにまとめる。

新美氏:「働くひとの西宇和みかん」「あなたの特命取材班」双方に共通しているのは、生活者とのコミュニケーション方法を変えることで、新たなコミュニティを作り出しているところ。みかんの流通を変えることで、(みかんを)食べてみようと(生活者が)思うようになったり、(身近な悩みを)新聞社に相談してみようと思うようになった。「これをやるんだ」という確固たる目的よりも、生活者からの作用を受けて、企業側がコミュニケーションの形を柔軟に変えているところがカギなのかもしれない。今後、メディアと生活者のコミュニティである「あなたの特命取材班」に企業が作用する可能性はあるのだろうか。
「あなたの特命取材班」で取り上げられた記事によって企業側が変革を起こし、社会課題の解決につながった事例もあるという。井関氏が語る。
井関氏:「九州を走る高速バスに障害者の優先席がない(から調査してほしい)」という調査依頼があり、記事化したところ、長崎のバス会社が実際に優先席を設置した。記事をきっかけに、企業が実際にアクションを起こしてくれた。

「報じるところまでがメディアの役割」としながらも、「その後の具体的な社会課題の解決にいたるまでの仕組みづくりも求められてくる」と井関氏。
井関氏:多くの人に実態を知らせるところまではできるが、その先の解決の部分、事業としての収益性・継続性をもって社会課題が解決される仕組みづくりについては(メディア単体では)できることに限界がある。「報じたあと、誰がどのように解決するか」という部分で企業との連携という道がある。(潜在的な問題を発掘する調査報道は)企業にとってニーズの掘り起こしにもつながる。問題解決まで、地域企業と一緒に実現していくことがこれからの(メディアの)役割になるのではないか。
地域社会というコミュニティにおいて、地元メディアの果たす役割は大きい。多接点時代における「地域密着メディア」としての地方新聞社のありかたにも井関氏は言及する。
井関氏:「地域密着メディア」としての不変的な役割に加えて、これから地方新聞社が担うべき新たな役割には、どんなものがあるだろうか?例えば「生活の困りごとや悩みの相談相手は?」というシチュエーションにおいて、自治体や友人のほかに「西日本新聞」という選択肢を想起してもらえる存在になれれば、新しいコミュニティ貢献の役割を担うことができる。地域に関する疑問を感じたとき「『あなたの特命相談室』に聞いてみよう」と想起してもらえるポジショニングをとれるよう、報道とコミュニティづくりを進化させていくことが大事だと考えている。
鷹觜氏は「働くひとの西宇和みかん」のPR戦略にも触れながら、産地に対する信頼感を持つ人々のコミュニティ作りを通じて、企業が生活者に対する「付加価値」を提供する可能性について述べた。
鷹觜氏:(「働くひとの西宇和みかん」は)出荷の1ヶ月前にPRを始めたことで、初荷前の話題化ができた。一般的なみかんの市場価格は1kg200〜300円程度だが、「働くひとの西宇和みかん」は送料込みだが、この価格を大きく上回る。農産品もデジタル上で、前倒しの戦略PRを利用していく時代になるのではと思う。
「売り場では、数円の違いを見てしまうが、(商品の価値を理解できる)情報を得ると、『応援したい、食べたい』という気持ちが売り場の価格差を超えていく」と鷹觜氏。
鷹觜氏:いろんな地域の食べ物とちゃんとつながっていられるという信頼感、安心感も新しい接点のカギになる。生活者とダイレクトにつながることで中間部分にかかっていたマージンが違う場所へと移行するが、そのお金をどこに移行させるべきか、そのお金を次に向けてどう役立てていくべきかについて考えをちゃんと持って発信していくことで、10〜20円といった購入価格の差では計れない価値を感じ、生活者が「ファン」から「ファミリー」になってくれる未来があると思う。

両者の発言を受け、「企業と生活者とのダイレクトなコミュニティは、非常に緩やかな連帯と、軽やかな機動力が特徴」と新美氏。「『ちょっとやってみよう』という試みが、思ってもなかった大きな動きにつながっていき、それがこれからのコミュニティをアップデートしていく存在になっていく」と締めくくった。