リアルタイムなVR体験はどう開発されているのか〜MBSグループ企業が展開するVR同時体験システム「どこでもVR」(後編)
マーケティングライター 天谷窓大
毎日放送、GAORAなどで構成されるMBSグループの新規事業創出会社「MBSイノベーションドライブ」の子会社であり、VR(仮想現実)技術を駆使するホラーコンテンツ制作会社『株式会社闇(やみ)』が2020年5月23日、VR同時体験システム「どこでもVR」をリリースした。
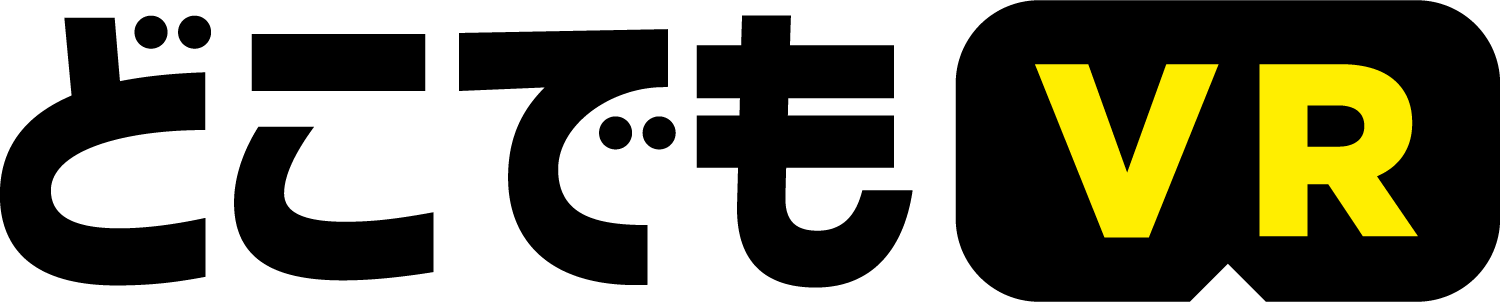
「どこでもVR」は映像作品インストール済みの4K高画質VRゴーグルと再生制御用タブレットで構成され、特別な技術や工事を必要とせずどんな場所でも簡単にVRイベントを実施できる。稼働にあたってインターネット回線は必要なく、これまで開催を断念してきたような場所での活用にも可能性が広がる。
後編となる今回は、そんな「どこでもVR」を支える開発体制について、そして闇が考えるこれからのVRコンテンツのかたちについて特集。前編に引き続き、株式会社闇 ディレクターの向後史朗氏、同テクニカルディレクターの久保田健二氏にリモートでインタビューする。
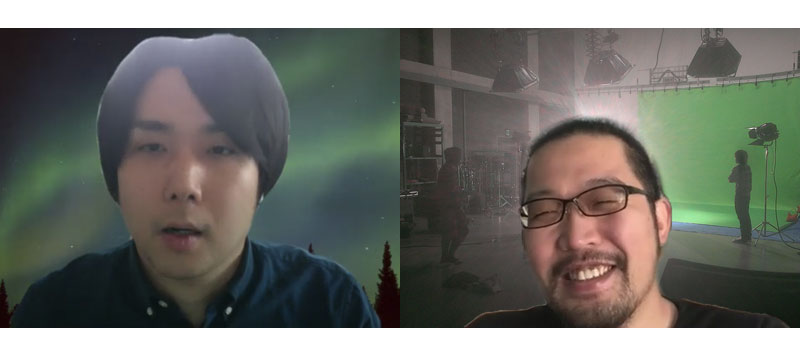
■制御用タブレットが「1/1,000,000秒単位」の処理をさばく
──「どこでもVR」ではインターネット回線を使用せず、VRゴーグルをタブレットから一括制御できるという点が印象的です。どのような技術によって構築されているのでしょうか。
久保田氏:VRゴーグルと制御用タブレットの間は、インターネットを介さないローカルネットワークで結ばれています。制御用タブレットがそのままWi-Fiのアクセスポイントとして機能する仕組みとなっており、各ゴーグルはタブレットに直接通信するかたちで機器操作用のデータをやりとりしています。

──タブレット側にはどのような技術が用いられているのでしょうか。
久保田氏:ベースとなる筐体はWinowsタブレットを使用していますが、OSとしてはLinux(*1)をインストールして利用しています。さらにGo言語(*2)で開発したサーバープログラムを内部で稼働させ、タブレット自体をミニサーバーとして機能させています。
(*1)Linux:オープンソースのOS(基本ソフト)。サーバーマシンや組み込みまで、さまざまな機器の制御に広く使われている。
(*2)Go言語:Googleによって開発されたオープンソースのプログラミング言語。大量・複数の処理を並行して行うことに長けている。
──Go言語はABEMAやNetflixなどの大手サービスでも続々採用されていますが、「どこでもVR」ではどのような経緯から導入を決めたのでしょうか。
久保田氏:(複数のゴーグルを同時に制御するため)並列処理に優れているという点がまず念頭にありました。細やかな制御のためには高速にレスポンスが行える必要があったのですが、Go言語で開発したローカルサーバーはマイクロ(1/1,000,000)秒単位でレスポンスを返すことができたのです。(Wi-Fiによる外部通信無しの場合)これまでPHP(*3)やJava(*4)といった他の言語での実装も試してきましたが、そのなかでもGoのパフォーマンスは圧倒 的に高く、こうした結果も踏まえて導入に踏み切りました。
(*3)PHP:The PHP Groupが開発しているオープンソースのプログラミング言語。ウェブページの動的な生成などに用いられる。
(*4)Java:Oracleが開発しているオープンソースのプログラミング言語。サーバープログラムから組み込み機器の制御まで、幅広い分野に用いられる。
──大量の処理リクエスト瞬時にをさばける、という点が決め手だったのですね。
久保田氏:この仕組を導入することで、タブレット1台あたりゴーグルを最大24台までド一括制御できることを確認しました。これ以上の数が必要となる場合も、制御用のタブレットを増設することによって柔軟に拡張が可能です。
余談ですがエンジニアとしては、Go言語はプログラム構文を書いていて楽しい、という側面も大きかったです。
(編注:Go言語は簡潔な構文を持ち、複雑な処理も比較的短いプログラムコードで実現できる)
■「リアルタイムVR」を支えるさまざまな技術
──VRゴーグルにおいても、再生タイミングや音量などの一斉同期が行える点が魅力的です。この仕組はどうやって実現されているのでしょうか。
久保田氏:ゴーグル内でVR動画の再生を制御するアプリケーションはUnity(*5)で構築しました。電池残量など機器に関するバイタルデータに関してはJavaで専用のAPIを開発し、アプリケーション側から参照できるようにしています。
(*5)Unity:Unity Technologies社が開発するゲームエンジン。高速なグラフィックや、物理法則を反映したリアルタイム描画などに優れている。
(*6)API:Application Programming Interfaceの略。機器間や複数の処理系をシステム間で連携させるための仕組み。
──VR制御においてはリアルタイム性が求められるとのことでしたが、再生や制御にかかわる機器はそれぞれ個別に時計を持っている関係上、動作にあたってはひとつひとつ正確に「時間合わせ」を行う必要があるかと思います。この課題はどのように担保しているのでしょうか。
久保田氏:時刻同期については、NTP(*7)を応用した時刻あわせシステムをローカル上で構築することで担保しています。NTPは基準となるサーバーからの情報にあわせて機器の時計を自動調整する仕組みですが、サーバーから対象機器へデータが到達するまでに生じるネットワーク遅延も考慮する設計となっており、より精密な時刻合わせを可能にしています。
(*7)NTP:Network Time Protocolの略。ネットワーク接続された機器の時計を正しい時刻に同期させるためのプロトコル(通信手順)。

■開発環境がコロナの影響を「受けなかった」理由
──新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、多くの企業ではテレワークの導入など職場環境の大幅な見直しが相次いでいます。「どこでもVR」の開発環境にも影響はありますか。
久保田氏:もともと2年ほどリモート体制で開発を行っていたので、今回のコロナウイルス感染拡大の影響は受けず、いつもと変わらず、といった感じです。
向後氏:闇は大阪で創業し、2年前に東京へ本社を移転したのですが、久保田は引き続き大阪に残り、Slack(*8)やFacetime(*9)などを駆使して連絡を取りながら開発に従事していました。コロナウイルス感染拡大を受け、今年3月下旬には全社的にもリモート勤務となりましたが、とくに連絡体制は変わっていません。
(*8)Slack:Slack Technologiesが提供するチームコミュニケーションツール。チャット画面を基本としたインターフェースで細やかな連絡共有に強みを持つ。
(*9)Facetime:Appleが提供するビデオ電話ツール。iPhoneやMacなどの機器同士で低遅延・高品質のビデオ通話が可能。
──もともと闇が導入していた先進的な働き方が、今回のコロナ禍でも活きたわけですね。
久保田氏:本社移転の際、私も東京(本社)へ呼ばれていたのですが、もともと自宅に工場を併設していたので「ものづくり」の環境が無くなってしまうことを避けたかったのと、週1回地元の大学で受け持っている授業に行くのが困難になるという理由から大阪に留まっていました。
──結果として柔軟な開発環境を維持しつつ、不測の事態にも影響を受けにくい体制ができあがったのですね。
■闇が目指すのは「日常生活中のホラー」
──今後のイベントづくりにあたって、闇としてはどんな分野や志向に関心を持っていますか。
向後氏:VRイベントを「リアルイベントの代替」として位置づけるのではなく、VRでこそできる体験を追い求めていきたいと考えています。リアルとデジタルのいいところを生かしつつ、これらのハイブリッドも模索しながら、安心安全なイベントのかたちを提案していけたらと思います。
久保田氏:たとえば町おこしの一環として「この場所はかつて城下町だった」というような地誌的な情報を位置情報に紐付けて記録し、体験者が同じ場所に立つと、その場所で起きた過去の出来事や、かつての風景などをタイムマシンのように体験できるVRを作れたら面白いですね。
向後氏:よりゲーム性の高い、インタラクティブなVRも今後作って行きたいと考えています。たとえばVR空間に選択肢があって、ストーリーが分岐するようなものです。
うなずいたり、首を横に振るなどのアクションに合わせてストーリーが分岐するような、より没入感の高い「自分ごと」になる体験を提供したいのです。これは「どこでもVR」のサービスで取り扱うことも想定しつつ、Steam(*10)など、世界中で体験できるようにも考えています。
(*10)Steam:Valve Corporationが提供する、ゲームを中心としたデジタルコンテンツ販売プラットフォーム。
久保田氏:イベントに行って怖い体験をするというのも良いですが、リアルな日常空間をゲームのステージにした『ポケモンGO』のように、日常生活の場をホラーな空間に変える仕組みづくりにも関心を持っています。
リラックスやストレス解消など人によって違いはあれど、普段と違う空間に「行く」ことによって心境の変化は起きるものだと思います。たとえば自分の部屋のなかにホラー空間を手軽に作り出せるような、日常生活の中の身近なホラーを実現できたらと思います。
「VRによって、より没入感のある世界体験を作り出したい」とする向後氏に、「ホラーはテクノロジーの実験場」と語る久保田氏。思えばもともとホラーは、感覚や想像といった人間が元来持つ力を拡張することで発展し、その営みとともに受け継がれてきた。アフターコロナ時代のイベントの形を考えるとき、これまで存在していた場所に対する新たなストーリーの付与というアプローチが大きなカギといえるかもしれない。