デジタルはチャンス!データ放送で誰もが楽しめるテレビを~中京テレビ「テレビ×デジタル」の取り組み(前編)
編集部
中京テレビでは独自にデータ放送を使用したCMやオリジナルコンテンツの配信を行なっており、「テレビ×デジタル」への取り組みを充実させてきた。2017年11月には、「CHUKYO-TV INNOVATION PROGRAM」と銘打ち、既存のテレビの枠にとどまらないコンテンツ産業における新規事業等を株式会社サムライインキュベートと共創、2018年5月末にはその成果を発表したばかりだ。
そこで今回は前後半に分けて、中京テレビが取り組む「テレビ×デジタル」に迫ったインタビューをお送りする。前半は、営業局営業推進部担当副部長・堀田茂紀氏、ビジネス推進局インターネット事業部担当副部長・森本英樹氏、株式会社中京エレクトロンシステム推進部・中島謙一氏の3名に、「テレビ×デジタル」の取り組み事例とその結果、そして今後の展望を語ってもらった。
■企業とコラボ!独自にデータ放送を使用したCMを配信
中京テレビは2018年3月、株式会社スギ薬局、ソフトバンク株式会社とそれぞれ協働し、データ放送、スマホを活用したCMを放送。これは、視聴者の行動によってリアルタイムに画面が変わるという画期的なものだった。CMの制作から配信に至るまでの経緯や取り組みはどういったものだったのだろうか。


堀田氏:生活者のメディア接触形態が変わっていく中には「テレビ離れ」という問題が大きく取り上げられがちですが、この取り組みを始めたのは営業寄りの視点から今後商品として販売していくことを視野に入れたことが大きな部分としてありました。そこでまず、「どうすればテレビのCMの価値を上げることができるのか?」というところから考えたわけです。

森本氏:もともと私と堀田は報道で一緒だったということもありますが、2年くらい前から「新しいことをやりたいよね」と話をする中で「データ放送には使っていない機能が沢山あるね」という話になったのです。データ放送といえば、いわゆる“L字”で情報が見られるというイメージがありますが、それだけではないのではないかと。技術スタッフから「オーバーレイ(L字ではなく、本線の上にスーパーのように表示する機能)で情報を出すことがきる」と聞いて、デモで見たときに「これは使える!」と実感しました。また、エリアで画像を出し分けすることもできることがわかり、これを使えば新しいCMの価値が創造できるのではないかと考えました。
堀田氏:世の中がデジタルシフトしている部分もあり、クライアントのニーズも変わってきています。細かなターゲティングを設定した配信や放送後のマーケティングを行えるようにしてほしいといった要望もありましたので、「CMでもデジタルを使おう」ということになりました。当社のインターネット事業部が持っていた技術を使えばいいものができるのではと、2つの企画(スギ薬局様とのデータ放送の企画、ソフトバンク様とのスマホの企画)を実施することにしました。
■見るCMから参加するCMに!

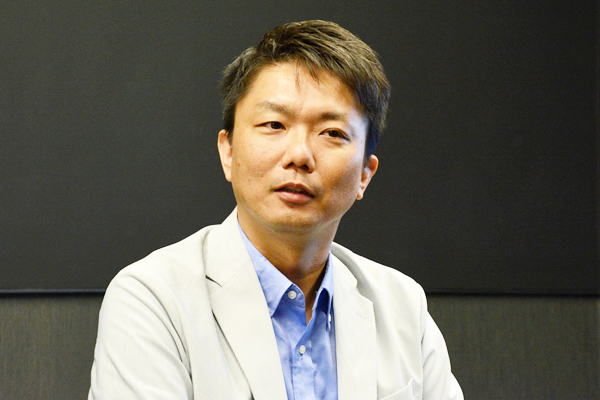
中島氏:スギ薬局様のCMでは、クイズを流して視聴者に回答してもらい、正解したらQRコードが表示されるものを作りました。
堀田氏:そのQRコードを読み取ればクーポンがもらえて、それをスギ薬局様の店舗で提示するとお茶やティッシュボックスといったノベルティがもらえるんです。
 全員同じ画面↑
全員同じ画面↑ 「除菌スプレー」「マスク」の選択肢はオーバーレイ表示↑
「除菌スプレー」「マスク」の選択肢はオーバーレイ表示↑ 正解、不正解者それぞれ画面が異なる
正解、不正解者それぞれ画面が異なる中島氏:特徴としては、通常のCMでは皆さん同じ画面を見るわけですが、この企画ではこの画面のように正解者には正解者用の画面、不正解者には不正解者用の画面、そして参加しなかった方はグレーの画面(写真:左上)と、3パターンの画面を出し分けできるわけです。
堀田氏:この企画では、50万世帯が見ていて、そのうち5万世帯が参加してくれました。もちろん課題も残りましたが、今回の企画についてスギ薬局様は「CMがちゃんと見られて、短い時間だったにも関わらず、これだけの人がボタンを押して参加してくれた=興味を持ってもらえた」と評価いただけました。
■スマホを使ったソフトバンクのCM事例
堀田氏:ソフトバンク様のCMは、株式会社HAROiDと一緒に制作しました。これは、CMを流している間にサイトへ訪問するとゲームに参加できるというものです。スマホに向かって「サンキューパス」と叫ぶと視聴者の声の数が集計され、リアルタイムで表示されます。音声を使ったものとしてはこれが初めてだったのではないでしょうか。
■実施後の効果について
堀田氏:ソフトバンク様の企画では、データが結構詳しくとれたというのが大きな収穫です。声を出して参加してくれた方、タップしてくれた方、プレゼントの応募までしてくれた方などの数字を追うことができました。スマホを使うということから、比較的若い方が多く参加してくれていました。4日間連続して行ったのですが、徐々に認知され参加者の数も伸びていきました。
森本氏:中京テレビはローカル局ならではのフレキシブルさで、比較的新しいことがやりやすい土壌があるんですよね。しかも、データ放送やCMを制作できるスタッフも局内にいるので、物理的にもできる体制が整っている。中京テレビだからこそ、今回の企画が実現できたのかなと思っています。
■データ放送で子どもも大人も楽しめるテレビを
中京テレビでは、2017年1月から、株式会社HAROiDと連携してデータ放送を活用した独自の子ども向けゲームコンテンツ「チュウキョ~くんランド」も配信している。その取り組み事例と狙いについて訊ねた。

森本氏:チュウキョ~くんランドは中京テレビのコーポレートキャラクターである「チュウキョ~くん」をメインキャラクターにしたゲームコンテンツです。チュリーという不思議な種を育てていく育成ゲームやカードゲーム、画面の中に隠れているチュウキョ~くんを探すゲームなど、いろんなミニゲームが楽しめます。主に未就学児童や小学生とその親がターゲットですね。また、ミヤギテレビと連携して、宮城県内で「だよんランド」も展開しています。基本的に内容は同じなのですが、だよんランドはメインキャラクターがチュウキョ~くんではなく、ミヤギテレビのキャラクター「だよん」になっています。
チュウキョ~くんランドを始めた背景には、「テレビ+データ放送」で人を集めたいという想いがありました。データ放送でゲームコンテンツを配信すれば、大人はテレビを観て、子どもはゲームを楽しむということが1つの画面で実現可能になります。ゲームをしている時は必然的に中京テレビがついていることになるので将来的には視聴率をアップさせる可能性も秘めている。こうしたコンテンツを配信することで、中京テレビを好きになってもらうことができて、ファン獲得につながると思っています。

データ放送を使ったゲームコンテンツの配信は単に視聴者を集める手段にとどまらない。今後の展開を聞いてみた。
森本氏:今後は系列局への展開を進める事と、コンテンツ自体を販売できるようになりたいですね。たとえばチュウキョ~くんランドの「ケーキやさんごっこ」という、素材を選んでケーキ作りを体験できるゲームがあるのですが、これをお菓子メーカーやケーキの販売店とタイアップすれば、新しい形のCMになるのかなと思います。あと、チュウキョ~くんランドは子どもがターゲットになっているのですが、今後は大人も楽しめるコンテンツを作っていきたいですね。実際、今「倉庫番」を制作中です。1982年に発売されたゲームなので、「子どもの頃に遊んだ」という経験がある大人の方も多いと思います。シンプルなゲームですが意外と難しくて、やり始めると熱中しちゃうんですよね。数多くの面があるので飽きずに楽しめると思います。
中島氏:画面を奪い合うのではなく、コンテンツでユーザーをテレビという媒体に引っ張るということができたらなと思います。ですから、他の局でもこうした取り組みをしてほしいと思っていますし、協働するとさらに面白いことができて、テレビ業界全体が盛り上がるのではないかなと考えています。
■課題は収穫、とれるデータは全部とる
データ放送・スマホを活用した様々な試みを行う中京テレビ。これまでの実績からどのような成果があり、どのような課題が見つかったのだろうか。
堀田氏:CMについては、今後いかに精度を上げていくかが課題だと思います。ただし、「課題が見つかった」ということも大きな成果なのかなと考えています。たとえば、スギ薬局様のCMは先ほどもお話ししたように、東海3県で50万世帯が視聴しました。そのうち1割の5万世帯がクイズに参加してくれたので、これは予想以上の成果だったと考えています。一方で、クイズの正解率が50%くらいだったので、クイズが難しかったかなとも思っています。他にもCMの長さを適切にしたり、ノベルティをいろいろ変えたりなど、考えていかなければいけないことがあることがわかりました。従来のCMと違ってデータを収集できるので、こうしたPDCAが回しやすいですね。今後はお店のPOSデータなどとも連携して、より詳細なデータをとっていければと思います。
森本氏:チュウキョ~くんランドに関しては、ユーザーの6割くらいは30代~40代というデータがとれています。これは親がログインした状態で子どもが利用しているということも考えられますし、本当に大人がゲームを楽しんでいる可能性も十分あります。今後はもっとデータを細分化し、子どもが使っているのか、大人が使っているのかといったデータも収集できるようにしたいですね。他にも、朝と夕方にアクセス数がアップする傾向があります。これは子どもが学校や幼稚園・保育園に行く前にゲームを楽しんで、帰宅したあとにもすぐテレビでゲームを楽しむというようなライフスタイルが背景にあると考えられます。
堀田氏:データ放送を活用することで、行動履歴や属性(年齢・性別など)が全てわかる時代となりました。まずはとれるデータは全てとるというスタンスで、さまざまな角度からデータを分析して、PDCAを回していきたいと思います。
■デジタルはピンチではない!チャンスだ!
最後に3氏に今後のテレビとデジタルの融合について、展望を語ってもらった。

堀田氏:従来のテレビ視聴者がデジタルに取られていると捉えている方も少なくありませんが、我々はむしろデジタルの発達はチャンスだと考えています。テレビとデジタルを融合させることで、CMの価値を上げることもできる。デジタルはテレビ業界にとってメリットも大きいと思います。今回の取り組みは最初の一歩。まだまだ大きな可能性があると思っています。
森本氏:テレビでもいい、スマホでもいい、パソコンでもいい。デジタルを使って、あらゆる場所で中京テレビが観られるようにしたいですね。個人的にはチュウキョ~くんランドをリアル化したいなと思っています。たとえばイベント会場でスマホを使ってチュウキョ~くんを見つけるとか、VRの技術を駆使してチュウキョ~くんの世界に入り込むとか。「テレビ×イベント×デジタル」という方向に発展させるのも面白いと思います。
中島氏:今までのテレビはマスに乗っかって、「同じものを同じ時間」が基本でした。今はそれがデジタル化によってだいぶ細分化されていると感じています。今後はデジタルを活用して個人のニーズに合わせたコンテンツを配信することが必要で、そのための技術を追い続けなければいけないかなと思っています。とれるデータは全部とって、PDCAを回す。そして、ユーザーのニーズを満たすコンテンツを、デジタルで実現したいですね。

後編では、「CHUKYO-TV INNOVATION PROGRAM」を推進した中京テレビビジネス推進局ビジネス開発部の鬼頭尚也氏にもお話を伺う。