ヤフーが本格的に乗り出す、ドキュメンタリー作家の創作活動支援とは?~Tokyo Docsとの連携理由~(前編)
ジャーナリスト 長谷川朋子
ヤフー株式会社(以下、ヤフー)がドキュメンタリーの国際共同製作を支援するイベント「Tokyo Docs(トーキョー・ドックス)」と連携し、ドキュメンタリー制作者の創作活動を支援する取り組みに本格的に乗り出す。ドキュメンタリー作品の実現化については制作資金の調達の問題のみならず、作品の放送先や配信先の確保の難しさなど、多くの課題を抱えている。そんななか、解決の道を探ろうと、国内最大級のネットメディアであるヤフーがクリエイターの制作支援を目的とした新たな取り組みを始める。放送局など既存のメディアとはどのような関係構築を想定しているのか。制作支援の先にはどのような事業の狙いがあるのだろうか。ヤフー株式会社メディア統括本部「クリエイターズプログラム」サービスマネージャー(事業責任者)の藤原光昭氏と同社メディア統括本部「クリエイターズプログラム」コンテンツプロデューサーの金川雄策氏のお二人に答えてもらった。
■ヤフーはなぜ、テレビ局や制作会社が参加するTokyo Docsと連携するのか?
放送局や制作会社、インディペンデントのドキュメンタリー制作者などが参加し、国際共同制作の成立を推進する業界イベント「Tokyo Docs」が毎年11月に都内で開催されている。その期間中、今年も実施が予定されている「ショート・ドキュメンタリー・ショーケース&ピッチ」部門にヤフーが初めて連携することになった。どのような経緯から、共同で取り組むことになったのだろうか。
 今年は11月5日~7日に日程で開催されるTokyo Docsの国際共同製作ドキュメンタリー企画会議(筆者提供)
今年は11月5日~7日に日程で開催されるTokyo Docsの国際共同製作ドキュメンタリー企画会議(筆者提供) 金川雄策氏
金川雄策氏金川氏:ヤフーでは各分野の専門家や有識者がオーサー(執筆者)として独自の視点による意見や提案を記事で寄稿する「ヤフーニュース個人」というサービスを2012年より続けてきました。昨年からはそのテストケースとして主にドキュメンタリー領域の映像クリエイターの制作や発信のお手伝いを始め、それがTokyo Docsとの連携に至ったきっかけになります。この1年の間、その新しい取り組みを行うなかで、様々な映像クリエイターの方と出会い、「山形国際ドキュメンタリー映画祭」や地域密着型のドキュメンタリーフェスティバルの「ドキュ・メメント」などにも足を運びました。そして、ある映像クリエイターからの紹介で昨年のTokyo Docsに顔を出させてもらったところ、日本から世界に向けてドキュメンタリー作品を積極的に広げていくというTokyo Docsの考え方が、我々が今後目指したい方向性と非常に近いものがあると感じました。今年はもう少し踏み込んで何か具体的なことができないかとTokyo Docs事務局の方々とお話をさせていただき、「ショート・ドキュメンタリー・ショーケース&ピッチ」部門と連携させてもらうことになりました。
 藤原光昭氏
藤原光昭氏藤原氏:映像クリエイターの中でもドキュメンタリー制作をされる方々は特に課題を多く抱えているのではと考えています。ドキュメンタリー作品が放送・配信される機会は決して多いとは言えず、良い作品が作られてもそれを届けられる場所が限られてしまっているのが現状です。制作資金を集めることの難しさもあります。Tokyo Docsはこうした課題を抱えているドキュメンタリーの映像クリエイターに対して育成や支援を継続的に行うことに理念を置かれていらっしゃいます。その理念とまさにこれからヤフーのメディア事業として実現していきたいビジョンやミッションがとても近いことを感じ、その実現に向けて、ヤフーもお手伝いしたいと思いました。
金川氏:当初は、インディペンデントで映像を作るクリエイターを対象に計画をしていましたが、ドキュメンタリー番組などの制作会社に所属されるクリエイターも同様に課題を抱えていることがわかりました。Tokyo Docsのようなピッチイベントに関しても、周りのサポートは少なく、自分たちで投資しなければならないうえに、回収する算段も明確には見えない中で企画提案をやっていかなければならないという現状があります。こういう課題に対して、私たちでも何かお手伝いできることがないかという観点から、この数ヶ月、様々な関係者の方々とも協議して、Tokyo Docsとの連携を始めることに至りました。
■制作資金のインセンティブを渡すスキームと著作権の考え
Tokyo Docsとの具体的な連携のかたちのひとつに制作支援金の援助がある。ヤフーが昨年からテストケースとして始めた映像クリエイターの制作・発信支援の取り組みは、新たに「Yahoo! JAPAN クリエイターズプログラム」という名称で、今秋にサービスがリリースされる予定だ。ドキュメンタリーに限らず、世の中の価値ある映像コンテンツをつくる様々なクリエイターたちを支援し、Yahoo! JAPANを通じてユーザーに届けてゆく新たな個人発信のプラットフォームが、この「Yahoo! JAPAN クリエイターズプログラム」である。
Tokyo Docsとの連携でいうと、このクリエイターズプログラムを通じて「ショート・ドキュメンタリー・ショーケース&ピッチ」部門に応募したドキュメンタリー制作者は、ヤフーからピッチ用の映像作品の制作支援金と宿泊・交通費等の経費が提供される仕組みとなっている。また、Tokyo Docsの「ショート・ドキュメンタリー・ショーケース&ピッチ」部門の選考対象となった映像作品は、国際共同制作への足がかりを手にいれるとともにヤフー上でも一部配信されることとなっており、広く一般のインターネットユーザーにも届けられる予定だ。なお、今年のTokyo Docsへの応募は9月10日(月)まで受け付けている。
金川氏:連携する大きな目的は、クリエイターの創作活動を支え、活躍できる場を作ることです。それがTokyo Docsと連携するヤフーの目的であり、役割だと思っています。制作資金をお渡しするスキームは我々がこれから立ち上げる「クリエイターズプログラム」のインセンティブプランを活用します。Tokyo Docsの事務局を通じて既にアナウンスし、登録応募を開始させて頂いております。Tokyo Docsの参加者の方の多くはピッチ用の作品づくりとしてオリジナル企画を考えていますから、まずは撮影や編集を行う際の最低限の制作コストの代わりとして、支援をさせてもらえればと考えています。
藤原氏:インセンティブによる制作コストの支援だけが目的ではありません。Yahoo! JAPANというプラットフォームをおおいに活用してもらって、クリエイターが伝えたい思いやメッセージを世の中に届けたり、自身が世間から認められたり、新しい出会いや仕事につなげてゆく。そういう世界を作りたいと考え、新たに事業として立ち上げるのがこの「Yahoo! JAPAN クリエイターズプログラム」です。

ヤフーのプラットフォームで配信されることが前提となるなか、映像の著作権についてはどのように考えているのだろうか。
金川氏:ヤフーで配信してもらいますが、著作権は全て制作者に留保されます。フッテージの全てを制作者が管理し、テレビでの放送や映画化が実現した際にもヤフーで配信されたフッテージを制作者の判断で使って頂ければと思います。ヤフーで配信される動画の尺についても特にルールを設けるわけではありませんが、インターネットにおける最適な推奨視聴時間という意味で10分〜15分前後を目安にしてもらうようにアドバイスをしています。Tokyo Docs側でも「グローイング・ショート」を意識されていて、短尺作品をきっかけにそれを長編作品へと成長させていこうとする思いは、まさに私たちが考えていることと同じ点で、これも今回の協力の背景にあります。
■クリエイター個人の活躍を支える仕組み
ドキュメンタリー制作者が抱えている課題は多岐にわたる。海外からも広く資金を得て制作する機会を広げ、海外のプロデューサーと共同制作を探ることも問題解決にも繋がる。そのために必要となる人的ネットワークの構築についてもヤフーは積極的に仕組みを整えてゆく考えだ。日本のテレビ放送局や映画会社といった世界に、クリエイター個人の活躍が広がってゆく道も見据えている。
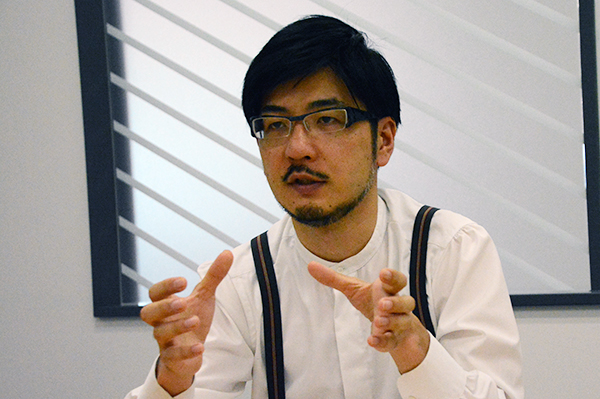
金川氏:Tokyo Docsとの連携のなかで、世界のメディアのディシジョンメーカーや関係者の方々と私たちがつながっているクリエイターたちとのマッチングの機会を提供できないかと計画しています。なかなか個人ひとりでは海外のメディア業界の人と知り合うことは難しいですから、こうした場を通じて、人脈を広げていただければと思います。またTokyo Docs主催の勉強会「Tokyo Docsアカデミー」にも参加して積極的に交流するなど、クリエイターの育成にも力を入れていきたいです。海外では様々な財団がフィルムメーカーを支援するスキームがすでにいくつもありますが、日本では若い学生向け以外にはなかなか見当たりません。我々がそうした役割を担うことも目指していきたいです。
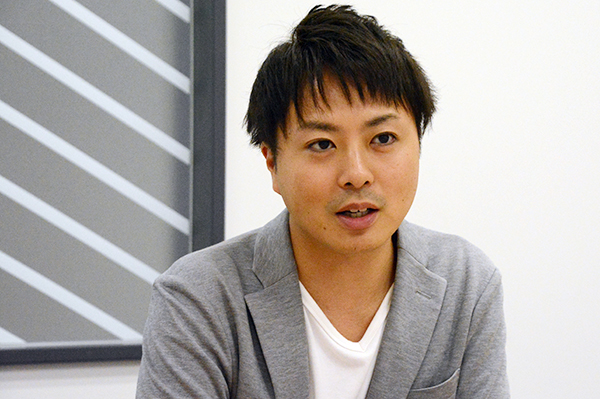
藤原氏:この1年の間、様々な映像クリエイターの方々とお話をしてきましたが、「人と関わりたい」というニーズはやはり多くあるように思います。それに対して、どのようにヤフーとして応えていくことができるのか。将来的にはビジネス的なスキームも視野に入れながら、プラットフォーマーの立場からオンライン・オフラインを含めて、クリエイターたちが活躍の幅を広げられる貴重な人的ネットワークの構築を模索していく予定です。Yahoo! JAPANがクリエイターを支援するプラットフォームになり、価値あるドキュメンタリー作品を継続的にユーザーに届けていき、そして、その発信や活動がきっかけとなって、テレビや映画、国際共同制作などの次のステップへとつながってゆけばよいなと。そういう意味で、我々はクリエイターにとって、”ゴール”としての「檜舞台」ではなく、そこに向かうための「ジャンプ台」になれればいいなと考えています。
金川氏:クリエイターの方々がヤフーの土壌の中で苗木を作っていくイメージですね。苗木を大きくしていくことを続けていくなかで、将来的には放送局や映画会社との連携も自然と作られていくのではないでしょうか。私自身、1年前まである大手新聞社に所属していましたが、メディア企業の中にいても発信する場を作ることはなかなか難しい部分もあります。日本国内における代表的なインターネットメディア企業として、少しでもクリエイターが活躍できる土台を作っていきたいと思います。
ヤフーが今年からTokyo Docsと具体的に連携するなかで、放送局から制作会社、インディペンデントまで幅広く、ドキュメンタリー制作者の活躍の場を国内にも世界にも広げていく機会が作られていくことに期待したい。いろいろな立場や視点で作られるドキュメンタリーによって今、日本や世界で起こっていることを知る機会にもつながっていくからだ。後編は前編にも触れたヤフーが計画する新たなサービス事業「Yahoo! JAPAN クリエイターズプログラム」を中心に、その狙いと可能性についてお伝えしたい。